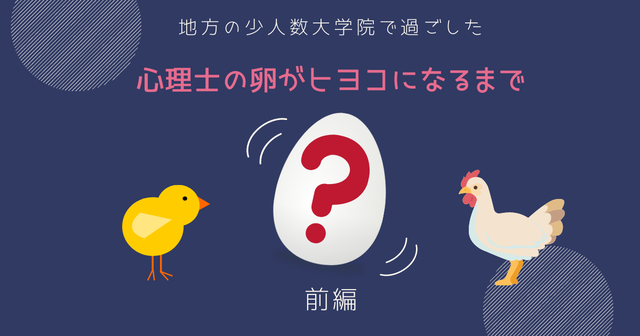
以前、ブログに臨床心理士と公認心理師、カウンセラーの違いについて触れました。
そこで記したように、臨床心理士という資格を取得するには、基本的に大学院に行き、修了後に臨床心理士試験を受けて合格することが一番の王道ルートと書いたのですが、じゃあその大学院って何するの?と聞かれることが結構あります。
今回は全編と後編に分けて、私の大学院生活を振り返りながら、お伝えしてみようと思います。
小規模な大学院ですごした2年間
私は青森県の大学に進学し、社会学や社会心理学を専攻している中で臨床心理士になりたいと思いが強まり、学部は別ですが同じ大学の大学院に進学をしました。
大学院は入学した時には同期が私の他に1人、上の代の先輩が5人、2年生になった時にできた後輩は2人と極めて小規模な大学院でした。
ただ、今振り返ると小規模ならではの大学院生活が送れていたんだなぁ~と入ってよかったと思っています。
臨床心理士になるために大学院でやることは大まかに、①授業、②研究活動、③実習、④カウンセリングのトレーニングにわけられます。
① 授業
これはイメージがしやすいかと思います。
大学院でも大学と同じように必修科目と、開かれているいくつかの講義から興味のあるものを必要な単位分選ぶ選択科目の授業にわかれていたのですが、私の大学院では授業を選択してしまうと先生とマンツーマン!なんてことも十分に有り得るので、基本的には開かれている全ての授業を受けるというのが文化でした。
そのお陰もあり、臨床心理学や心理検査に関する知識だけではなく、家族心理、発達心理、統計学、基礎心理学、心身医学、社会心理学、心理関連行政・・・などなど幅広く知識をつけられたと感じています。夏休みや春休みには関東など外部の先生をお招きしての集中講義もありました。
大学院って大学より随分と忙しいんだなぁ・・・と当たり前に感じていましたが、今成績表を見返すと、卒業に必要な単位の1.6倍の授業を履修していました!笑
② 研究活動
大学院といえば、研究!そんなイメージがあるのではないでしょうか。
私は、当時からトラウマについて関心があり、傷ついた体験の有無やその質、現在生じているトラウマ反応の掛け合わせで精神的な健康度はどのような違いがあるのかということをテーマに研究をしていました。
また、東北地方の大学院の学生同士で声を掛け合い、定期的に勉強会として修士論文の経過や内容について発表する場を設けていました。
岩手や宮城の他の大学に行くときにはプチ修学旅行のような気持ちで楽しかったのを覚えています。
さらに、私の所属していた研究室の先生は、積極的に修士論文の途中経過を学会でポスター発表することや、完成した修士論文を学会に投稿することをすすめてくださる先生で、先生のご指導のおかげで心理臨床学研究に修士論文の一部を掲載してもらうことができました(松田侑子先生ありがとうございます!!)
修士論文の他には、授業でも学生全員で研究テーマを決めて一つの研究を行い紀要(大学院で出す刊行物)に投稿する取り組みがあり、修士論文とはまた違って先輩や後輩と一緒に研究をすすめる難しさや面白さを感じていました
・・・書いていると当時の色んな記憶が蘇ってきますねぇ。懐かしい。
のこりの③実習、④カウンセリングのトレーニングについては、後編の記事に書こうと思います。
